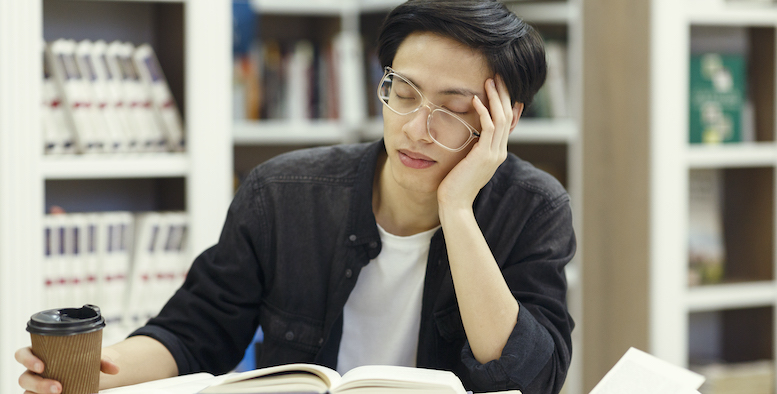柑橘類の摂取とうつ症状の軽減には関連がある可能性があり、その効果には腸内細菌「ファエカリバクテリウム・プラウスニッツィ(F. prausnitzii)」が関与している――そんな興味深い研究結果が、ハーバード大学と中国の研究機関によって発表されました。
みかんやオレンジなどの柑橘類をよく食べる人ほど、うつ症状が軽くなる傾向があり、腸内環境がその関係を“仲介”している可能性があるというのです。
F. prausnitzii potentially modulates the association between citrus intake and depression | Microbiome | Full Text
https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-024-01961-3
Eating citrus may lower depression risk — Harvard Gazette
https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/02/eating-citrus-may-lower-depression-risk/
柑橘類の摂取とうつ症状に相関関係
ハーバード大学などの研究チームは、複数の健康データベースを用い、果物の摂取頻度とうつ症状との関係を調査。
その結果、柑橘類(オレンジ、グレープフルーツ、みかんなど)を頻繁に摂取する人ほど、自己申告によるうつ傾向が少ないことがわかりました。特に女性では、この傾向がより顕著に見られました。
腸内細菌「F. prausnitzii」がカギを握る?
研究の注目点は、柑橘類とうつ症状の関連に、特定の腸内細菌が関与している可能性が示されたことです。
中でも「F. prausnitzii(ファエカリバクテリウム・プラウスニッツィ)」という腸内常在菌の存在量が、柑橘類の影響を“強める”働きをしていると考えられています。
この菌は抗炎症作用で知られ、腸内の健康維持に寄与することで知られています。うつ症状には炎症が関係しているという説もあり、F. prausnitzii の存在が精神的健康に寄与している可能性があります。
腸脳相関が示す「食とメンタル」のつながり
この研究は、腸内環境が脳や気分に影響を与える「腸脳相関(Gut-Brain Axis)」という概念を裏付けるものとしても注目されています。
食べ物が直接脳に働きかけるのではなく、腸内細菌が介在することで、精神的な健康状態が左右されるという新しい視点を提供しています。
食習慣がもたらす身近なメンタルケアの可能性
研究者らは「柑橘類は手軽で多くの人に取り入れやすい食品であり、食生活の中でうつ予防に活かせる可能性がある」と強調しています。
また、F. prausnitzii を増やすためには、食物繊維や発酵食品をバランスよく取り入れる食事も有効とされます。
現時点では因果関係の証明までは至っていないものの、「日々の食習慣がメンタルヘルスに影響を与える」という可能性を示した本研究は、今後の栄養学・精神医学における重要な視点となりそうです。
文=WEBOPI(翻訳・編集)